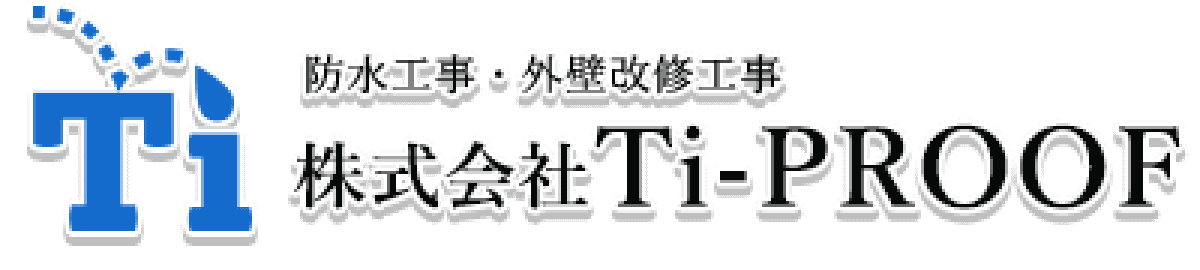防水工事の費用はいくら?工法別・施工箇所別の相場や見積もりの注意点など


防水工事は、建物の劣化や雨漏りを防ぐために欠かせません。しかし工法や施工箇所によって工事費用は大きく異なるため、適切な相場を知っておくことが大切です。そこで本記事では、防水工事費用の相場を工法別・施工箇所別に解説します。見積もりを取る際の注意点や費用を抑えるコツもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- 防水工事の費用はいくら?
- 工法別の防水工事費用の相場
- 施工箇所別の防水工事費用の相場
- 防水工事費用の見積もりを取る際のチェックポイント
- 防水工事費用を抑えるコツ
- 費用以外の防水工事に関する注意点
- まとめ:防水工事費用は業者選びで大きく変わる
防水工事の費用はいくら?

防水工事の費用は、工法や施工面積、建物の劣化状況などによって大きく異なります。初めて工事を依頼する場合には、「思ったより高い」「見積もりの根拠がわからない」と感じてしまうことがあります。
そこで防水工事費用の相場や費用に影響する要素、建物の種類による違いを分かりやすく解説します。「適切な見積もりかどうか」を判断できるように、費用相場を把握しておきましょう。
防水工事費用の相場
防水工事費用の相場は、1㎡あたり2,000〜10,000円程度です。たとえば100㎡の防水工事には、20万~100万円程度がかかります。
なぜ相場に幅があるのかというと、工法や施工箇所、劣化状況などによってコストが変動するためです。同じ工法でも、下地の状態や事前の処理作業の有無によって金額が上下するケースもあります。
そのため、複数の業者から相見積もりを取ることが大切です。安さだけで判断せず、見積もりの内訳や工法の説明をしっかり受けたうえで、納得できる内容を選びましょう。
費用を左右する要因(工法・施工面積・劣化状況・下地処理など)
防水工事の費用は、次のような要因によって決まります。
- 工法
- 施工面積
- 建物の劣化状況
- 下地処理の有無
まず工法についてですが、複数の種類(ウレタン防水・FRP防水・シート防水、アスファルト防水など)があり、それぞれ材料費と施工の手間が異なります。たとえばウレタン防水は比較的リーズナブルですが、耐久性の高いFRP防水の費用はやや高めです。
次に施工面積が広ければ広いほど材料費・人件費がかさむため、工事費用が高くなります。ただし単価は下がる傾向にあり、広範囲で施工する場合は1㎡あたりの費用が割安になることもあります。
さらに、建物の劣化状況も無視できません。ひび割れや雨漏りが進行していると、施工前に下地の補修が必要になるため、追加費用が発生します。下地処理の内容(高圧洗浄やひび割れ補修、プライマー塗布など)も、コストに影響します。
以上のように、防水工事費用はさまざまな要素に左右されます。㎡単価だけで判断せず、見積もりの詳細をよく確認することが重要です。
建物の種類による違い(戸建て住宅・マンション・オフィスビルなど)
建物の種類によって、防水工事の内容と費用が大きく異なります。特に戸建て住宅とマンション、オフィスビルでは工法も規模も異なるため、相場感を把握しておくことが大切です。
- 戸建て住宅 :小規模なため、マンションよりは費用がかからない
- マンション :大規模なため、100万円以上かかることもある
- オフィスビル:特別な対応を依頼すると、費用が高くなる
まず戸建て住宅の場合は、主に屋上やベランダ、バルコニーといった比較的小規模な範囲のため、数十万円程度で収まります。個人所有のため、工事の日程や内容を柔軟に決められる点も特徴です。
一方で、マンションの場合は共用部分を対象とするため、施工面積が広くなります。管理組合が主導して業者を選定し、建物全体の構造や耐久性を考慮した施工が求められます。1件あたりの費用が、100万円以上になることも珍しくありません。
さらにオフィスビルや商業施設などでは、施工時間の制約(夜間工事・休日対応)や防音対策、仮設施設などが必要になると、費用が高額になります。
建物の規模や用途によって、防水工事にかかるコストが大きく変動することを覚えておきましょう。
工法別の防水工事費用の相場

防水工事の費用は、工法によって大きく変わります。工法ごとに難易度や耐久性、適した場所が異なるため、それぞれの特性と費用感を把握しておくことが重要です。それでは代表的な4つの防水工法について、相場価格や特徴を詳しくご紹介します。
ウレタン防水
ウレタン防水の工事費用と特徴をご確認ください。
- 1㎡あたり3,000〜7,000円程度が相場である
- 耐久性は10年前後である
- 液体状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する
- 幅広い箇所に使用できる
ウレタン防水のメリットは、複雑な形状の場所にも対応できる柔軟性の高さです。継ぎ目がないため、漏水するリスクがシート防水よりも少ないです。また軽量で建物への負担が少ないので、改修工事に適しています。
ただし職人の技術によって仕上がりの質が左右されるため、業者選びを慎重に行う必要があります。塗りムラがあると、効果が十分に発揮されない恐れがあるためです。安定した防水効果を得たい場合は、経験豊富な業者を選びましょう。
ウレタン防水工事についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
https://ti-proof.com/column/urethane-waterproofing-work
シート防水
シート防水の工事費用と特徴は、以下のとおりです。
- 1㎡あたり4,000〜8,000円程度が相場である
- 耐久性は15年前後である
- 塩ビやゴムのシートを防水層として施工する
- 面積の広い屋根や屋上などに使用される
シート防水のメリットは、工場で作られた防水シートを使用するため、品質が安定しやすいことです。また施工期間も比較的短く済むため、工期を急ぐ現場に向いています。紫外線や熱への耐性にも優れています。
一方で、複雑な形状の場所や凹凸の多い下地には不向きなことがあります。また下地の状態が悪い場合には補修作業が必要になるため、事前の現地調査が必要です。施工性の高さと耐久性のバランスを重視したい場合におすすめの工法です。
FRP防水
FRP防水の工事費用と特徴もチェックしましょう。
- 1㎡あたり6,000〜9,000円程度が相場である
- 耐久性は15年前後である
- ガラス繊維を混ぜた樹脂を塗布し、非常に硬くて強い防水層を形成する(※)
- 主にベランダや屋上、バルコニーなどの平面の箇所に用いられる
※FRPはFiber Reinforces Plastics(繊維強化プラスチック)の略称です。
FRP防水のメリットは、非常に高い耐久性と耐摩耗性です。固く仕上がるため、歩行や荷重のかかる場所にも向いています。また施工後すぐに歩行が可能になるため、日常生活への影響が少なくて済む工法です。
ただし下地が動くような木造住宅ではひび割れを起こしやすいため、施工箇所を検討する必要があります。また費用がやや高めになるため、長期的なコストパフォーマンスを考慮しましょう。
アスファルト防水
アスファルト防水の工事費用と特徴もご紹介します。
- 1㎡あたり7,000〜10,000円程度が相場である
- 耐久性は20年前後である
- アスファルトを加熱して溶かし、防水シートと交互に積層していく
- 主に大規模建築の屋上や屋根などに採用される
アスファルト防水の特長は、耐久性の高さと耐用年数の長さです。適切な施工とメンテナンスを行えば20年以上持つこともあり、ビルやマンションの屋上防水として広く使われています。また熱や薬品にも強いため、過酷な環境でも安定した防水性能を維持できます。
一方で、施工には専用の設備や火気の使用が必要となるため、一般住宅には向かない場合もあります。また工期が長くなる点や作業時の臭いも、アスファルト防水のデメリットです。高い耐久性を求める大規模建築に適した工法です。
施工箇所別の防水工事費用の相場

防水工事費用は、施工する場所によっても大きく異なります。屋上・バルコニー・ベランダ・浴室など、それぞれに適した工法と費用感があります。それでは、主要な施工箇所ごとの相場と特徴を確認しましょう。
屋上・バルコニー
屋上やバルコニーの防水工事の費用相場と工法をご紹介します。
- 1㎡あたり5,000〜10,000円程度が相場である
- ウレタン防水やシート防水、FRP防水、アスファルト防水が用いられる
たとえば20㎡の屋上にウレタン防水を施すと、一般的に10万円前後の費用がかかります。ただし既存の防水層を撤去する必要がある場合や下地補修が必要になる場合は、コストが上乗せされます。
屋上・バルコニーは直射日光や雨風を直接受けるため、防水性能が低下しやすい箇所です。屋上・バルコニーの劣化が進行すると雨漏りや構造体の劣化につながるため、定期的なメンテナンスや防水工事が重要です。
屋上やバルコニーは建物全体の寿命に関わる重要な箇所ですので、価格だけでなく品質や保証内容を含めて検討しましょう。
ベランダ・外階段
ベランダや外階段の防水工事の費用相場と工法もご確認ください。
- 1㎡あたり4,000〜8,000円程度が相場である
- 歩行や荷重に強い工法(FRP防水やウレタン防水)が選ばれる
ベランダは人が頻繁に出入りし、物干しや荷物の搬入などで摩耗しやすいため、防水層に強度が必要です。特に雨水が溜まりやすい箇所を放置すると、内部への浸水やカビの原因になります。
外階段も同様で、常に雨風にさらされる場所でありながら、安全性も求められるため、防滑性のある塗装や厚みのある防水層が必要です。FRP防水なら施工後すぐに歩行が可能で、耐摩耗性にも優れているため、ベランダ・階段に適しています。
ただし下地の材質(金属や木材など)によって適した工法が変わるため、業者による施工前の現地調査が重要です。
ベランダ防水工事についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
https://ti-proof.com/column/veranda-waterproofing-work
浴室や室内
浴室や室内の防水工事は、
- 1㎡あたり3,000〜6,000円程度が相場である
- 主にウレタン防水やシート防水、FRP防水が用いられる
浴室や室内の施工範囲は狭いため、防水工事費用の相場は1箇所あたり5万〜15万円程度です。ただし狭い範囲でも工事の難易度が高いため、費用が割高になる場合もあります。
防水層の再施工や漏水対策としては、一般的にウレタン系の塗膜防水が採用されます。
水まわりは生活に大きく影響し、漏水が発生すると階下への被害やリフォーム費用が発生してしまいます。特に築年数の経過した戸建て住宅やマンションでは、防水性能が低下していきます。浴室の床や壁のタイルのひび割れ、洗面所・トイレ周辺の床のシミなどがあれば、早めに補修を行うと安心です。
日々の生活でよく利用する浴室や室内にトラブルが起きてからでは遅いため、早めの対策を心がけましょう。
防水工事費用の見積もりを取る際のチェックポイント

防水工事の見積もりを取る際は、単に金額だけを見るのではなく、工事の詳細や業者の対応までしっかり確認することが重要です。そこで、見積書でチェックすべき基本項目や金額の落とし穴、保証期間、接客対応といったポイントを解説します。
基本的な項目
防水工事の見積もりには、「工事の内訳」が明確に記載されていることが重要です。工事の詳細が曖昧な見積書では、信頼性に欠けます。明細がないと「何にいくらかかっているのか」がわからず、契約後に「追加費用」を請求されるリスクもあるのです。
信頼性の高い見積書には、以下の基本的な項目が含まれています。
- 工法の種類(例:ウレタン防水2層仕上げ)
- 施工面積(例:20㎡)
- 金額の内訳(例:材料費・人件費・諸経費)
- 下地処理(ひび割れ補修や高圧洗浄など)の有無
- 付帯作業の内容(例:養生・清掃など)
たとえば「防水工事一式30万円」などと大雑把に書かれている見積書では、具体的な工法や施工面積、下地処理の有無などが不明で、価格の妥当性を判断できません。基本的な項目がしっかりと書かれている請求書を受け取ることで、後悔のない工事につながります。
相場よりも安すぎる金額
相場よりも極端に安い見積もりには、注意が必要です。「安さ」だけで判断しても、あとから追加費用が発生するリスクがあるからです。
相場よりも安すぎる金額の見積書には、以下の理由が考えられます。
- 材料の質を落としてコストを削っている
- 作業の工程を省略している
- 経験の浅い作業員が施工している
- 工事後のアフターフォローがない
たとえば通常なら2層塗りが必要なウレタン防水を1層だけで仕上げてしまえば、表面上は同じに見えて耐久性が落ちてしまいます。また工事後にトラブルが発生しても、「保証がない」「連絡がつかない」といったケースもあるのです。
もちろん企業努力によってコストを抑えている良心的な業者もいますが、「価格の妥当性を丁寧に説明してくれるか」が、工事業者を見極めるポイントです。
保証期間やアフターフォローの有無
防水工事を依頼する際は、必ず保証期間やアフターフォローの有無を確認しましょう。外見だけでは防水層の劣化に気づきにくく、施工後しばらく経ってから問題が発覚するケースがあるためです。
防水工事の保証期間は、一般的に5~10年程度です。
- 「防水層の剥がれやひび割れ」「施工ミスによる雨漏り」などが保証される
- 工法や施工範囲などによって保証内容は異なる
- 見積書や契約前の説明で確認することが大切です。
保証期間だけでなく、アフターフォローの有無も重要です。以下の点を確認しましょう。
- 万が一不具合があった際に、迅速に対応してもらえるか
- 相談窓口はあるか
信頼できる業者であれば保証書を発行し、連絡先や対応方法を明示してくれるはずです。防水工事の費用だけではなく、安心材料も重視しましょう。
工事業者の接客対応
見積もりの段階で、業者の接客対応を見極めることも非常に重要です。丁寧で誠実な対応をしてくれる業者なら、施工後のトラブルを未然に防ぐように努め、トラブルが発生しても迅速に対応してくれます。
たとえば質問に対して曖昧な答えしか出さない業者や専門用語ばかりを用いて説明する業者は、顧客目線に立っていません。一方で、素人でも理解できるように、工法の違いや金額の根拠を丁寧に説明してくれる業者は、信頼性が高いです。
また見積もり時の服装や言葉遣い、時間を守る姿勢などもチェックポイントです。小さなことに見えますが、丁寧な接客対応が現場の施工品質にも表れます。金額や工法だけでなく、「この業者に任せて大丈夫か?」という安心感も判断基準にしてください。
防水工事費用を抑えるコツ

防水工事は決して安くはありませんが、工夫次第で費用を抑えることができます。信頼できる業者の選び方や不要な工事を避ける方法、定期的なメンテナンス、公的な補助金・助成金制度まで、費用を節約するための具体的なコツをご紹介します。
信頼できる業者を選ぶ
防水工事費用を抑えるうえで、まずは信頼できる業者を選ぶことが重要です。実績が豊富で技術力の高い業者であれば、適切な工法と工事内容を選択し、長い目で見たときのコスト削減につながります。
見積もりを取る際には金額だけでなく、以下の点も判断材料にしましょう。
- 対応の丁寧さや説明の分かりやすさ
- 施工実績の豊富さ
- 保証期間やアフターフォローの有無
経験が浅い業者に依頼すると、施工のミスや早期の劣化が発生し、再工事が必要になることがあり、かえって高くついてしまいます。一方で、評判の良い業者は現地調査や説明が丁寧で、費用や工期に対して納得感のある提案を期待できます。長く安心できる施工を実現するためにも、業者選びはじっくり時間をかけて行うことが重要です。
余分な工事を減らす
防水工事費用を抑えるには、本当に必要な工事だけを行うことも重要です。無駄な作業を省けば、人件費や材料費を節約できます。施工業者によっては「ついでにやっておきましょう」と、必要以上の工事を勧めてくることもあります。
- 部分的な下地処理だけで済むケースがある
- 必ずしも劣化していない箇所まで全面的に施工する必要はない
そこで有効なのが、相見積もりを取ることです。複数の業者に同じ条件で見積もりを依頼すれば、過剰な工事や価格のズレに気づきやすくなります。また建物の状態を写真に撮って自分でもチェックしておくと、業者とのやり取りがスムーズになります。
不要な工事を減らすことで、合計金額を賢くコントロールしましょう。費用を抑えた防水層のメンテナンスについては、インスタの投稿もご覧ください。
定期的なメンテナンスを心がける
防水工事の出費を削減するには、定期的なメンテナンスも効果的です。こまめに点検・補修をすることで防水層の劣化を抑え、大規模な工事を避けられます。
- 防水層は紫外線や雨風の影響で徐々に劣化する
- 早い段階でひび割れや剥がれに気づけば、小規模な補修で済む
- トップコートの塗り直しや簡単なコーキング補修などで費用を抑えられる
メンテナンスを怠り劣化が進んでしまうと、全面的な再施工が必要になってしまいます。特に屋上やバルコニーは劣化しやすいため、5年に一度の点検を目安にしておくと安心です。小さな不具合を見逃さず、コストを最小限に抑えるメンテナンスを心がけましょう。
国・地方自治体の補助金・助成金制度を活用する
防水工事費用を抑えたいなら、補助金・助成金制度の活用も検討しましょう。申請条件に合えば、工事費用の一部を国や自治体が負担してくれます。
- 建築物の長寿命化や省エネ化などを支援している
- 防水工事を含むリフォームに対して数万〜数十万円を支給している
一般的な補助金・助成金制度の申請には事前の承認が必要で、「工事前に申請しなければ対象外」となることがあります。また補助金・助成金には予算枠があり、審査を受ける必要がある場合や途中で募集が締め切られる場合があります。
「防水工事 補助金 助成金 地域名」でWeb検索すると最新情報が見つかりますので、工事を検討している方はぜひチェックしてみてください。例えば埼玉県越谷市では、越谷市住宅・店舗改修促進補助金の制度を運用しています(※)。
※参照元:埼玉県越谷市「令和7年度 越谷市住宅・店舗改修促進補助金(第1期)について」
(https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/sumai/sien/kaisyusokusin2025-1.html)
費用以外の防水工事に関する注意点

防水工事では費用ばかりに目がいきがちですが、工事のタイミングや生活への影響、防水層の耐用年数などにも注意しなければなりません。長期的な安心につながる費用以外の注意点について、わかりやすく解説します。
施工の時期や天候
「防水工事をいつ行うか」によって仕上がりや工期に影響を与えるため、時期や天候も重要なポイントです。温湿度や雨量などに配慮して、防水工事に適したタイミングで依頼しましょう。
- 防水工事には乾燥工程がある
- 梅雨や寒冷期には防水層が乾きにくく、施工不良の原因になりやすい
- 特にウレタンやFRPなどの塗膜系防水は、温湿度が仕上がりに大きく影響する
- 気候が安定していて晴れが続く時期が工事に適している
天候が不安定な時期に着工すると、雨天による中断や工期の延長が発生するリスクもあります。可能であれば天気予報を確認しながら余裕をもった日程で工事予定を組み、業者とも綿密に相談してスムーズな施工を心がけましょう。
工事中の悪影響(洗濯・騒音・業者の出入り)
防水工事中には、日常生活に影響を与えるリスクがあります。工事によるストレスを軽減するためには、事前に生活への影響を理解したうえで対策を講じておくことが重要です。
特に、洗濯と騒音、業者の出入りに注意しましょう。
- ベランダやバルコニーが施工箇所の場合には、部屋干しを余儀なくされる
- 施工箇所以外の場所に外干しをすると、防水材の臭いやホコリが付く恐れがある
- 工事中には、作業音や足音による騒音が発生する
- 事前に挨拶回りをしてくれる業者を選ぶと、近隣に配慮できる
- 業者が頻繁に出入りしてプライバシーが気になる
- 施工のスケジュールや時間帯を業者と相談する
事前の説明が丁寧な業者を選べば、生活スタイルに合わせた対応を相談して、安心して工事期間を過ごしやすくなります。
耐用年数
防水工事を行う際は、費用だけでなく「どのくらいの期間だけ防水効果が持続するのか」にも注目しましょう。耐用年数を把握しておくことで、無駄な再施工や予期せぬ修繕のコストを削減できます。
防水工事にはいくつかの工法がありますが、それぞれ耐用年数が異なります。
- ウレタン防水 :10年前後
- シート防水 :15年前後
- FRP防水 :15年前後
- アスファルト防水:20年前後
ただし、上記の目安は適切な施工と定期的なメンテナンスが行われた場合の年数です。実際には、紫外線や風雨の影響、施工環境などによって耐用年数が短くなる可能性があります。見積もりを取る際には「この工法の耐久性はどのくらいか」「何年間の保証・アフターサービスがあるか」を確認し、長期的に見たコストパフォーマンスを考慮することが大切です。
まとめ:防水工事費用は業者選びで大きく変わる
防水工事費用は、工法や施工箇所だけでなく、業者の選び方によっても大きく変動します。見積もりの内訳や保証内容をしっかり確認したうえで信頼できる業者に依頼することが、コストを抑えつつ高品質な仕上がりを得るためのポイントです。
Ti-PROOFでは、専門的な知識と豊富な実績をもとに、お客様の所有する建物に適した防水工事をご提案しています。
確かな品質と安心のアフターサービスで、建物の資産価値を守りますので、まずはお気軽にご相談ください。