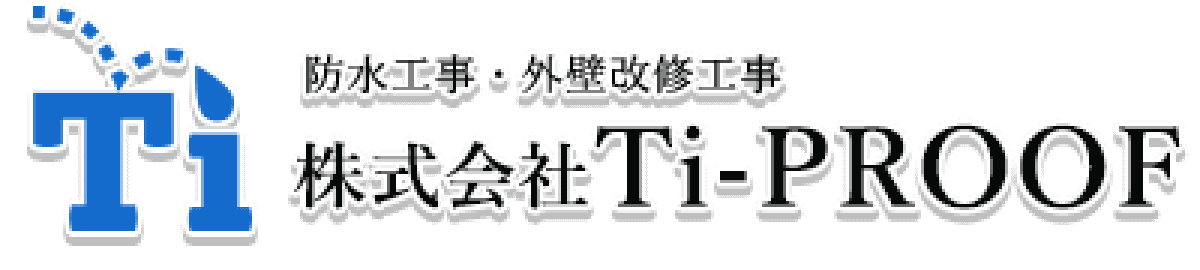防水工事の種類を解説!代表的な工法の特徴と選び方や工事費用など


防水工事は、雨や湿気から建物を守るために欠かせない工事です。使用される防水工法にはいくつかの種類があり、建物の場所や構造によって適した方法が異なります。そこで本記事では、代表的な防水工事の種類とそれぞれの特徴、選び方のポイントをわかりやすく解説します。
防水工事とは?基礎知識を確認

防水工事とは、建物内部への水の浸入を防ぐために行う施工です。雨漏りや結露などを防ぎ、建物の寿命を延ばすために欠かせません。それでは防水工事の重要性や施工が必要な場所、適切な時期、止水工事との違い、DIYについて詳しく解説します。
防水工事の重要性
防水工事は、建物を長く快適に使い続けるために非常に重要です。防水が不十分な状態では、雨水や湿気が室内に侵入し、建物の構造部分が劣化してしまいます。
例えば鉄筋コンクリートに水が浸み込むとひび割れが進行し、鉄筋がさびて強度が低下するリスクがあります。また湿気がたまることでカビが発生し、住環境にも悪影響を及ぼします。特に木造住宅では、木材が腐食してシロアリ被害につながることもあるのです。
以上のように、建物の資産価値や住む人の健康を守るために、防水工事は欠かせません。防水工事は建物の見えない部分を守り、快適で安全な生活を支える大切な役割を担っています。
防水工事が必要な場所
防水工事が必要となる場所は、建物の中でも特に水に触れやすい箇所です。
- 屋外(屋上・バルコニー・ベランダ)
- 室内(浴室・洗面所・キッチン)
- 地下(地下室や基礎)
屋上・バルコニー・ベランダなどの屋外部分は直接雨風を受けるため、劣化しやすい箇所です。浴室や洗面所、キッチンなどの水回りは水がこぼれやすく、床や壁に水分が染み込むと内部腐食やカビの原因になります。地下室や基礎部分は地面の水分が常に接触しているため、放置すると水が浸入して室内に湿気がたまる原因になるのです。
したがって屋外・屋内・地下を問わず、水がかかる場所や湿気がこもる部分には、防水工事が必要になります。
防水工事の適切なタイミング
建物の状態や築年数などに応じて、適切なタイミング(施工から10~20年程度)で防水工事を行うことが重要です。一般的には新築時に防水処理が施されますが、経年劣化により機能が低下していくため、定期的な点検と再施工が必要になります。
防水工事の頻度(耐用年数)の目安は、以下の通りです。
- ウレタン防水 :10〜12年程度
- シート防水 :10〜15年程度
- FRP防水 :10~15年程度
- アスファルト防水:15〜20年程度
※ただし施工箇所の環境や気候、利用状況などによって、耐用年数は変動します。
耐用年数を過ぎると防水層が劣化し、ひび割れや膨れ、はがれなどの症状が発生するようになります。室内に雨染みが出始めたり、ベランダの床がふわふわしたりするといった兆候が出たら、早急に点検と修繕を手配しましょう。トラブルが起きてからでは遅いため、10年を目安に専門業者による診断を受けるのが安心です。
止水工事との違い
止水工事は防水工事と混同されやすいのですが、工事の目的や方法が違います。
| 工事の種類 | 防水工事 | 止水工事 |
| 目的 | あらかじめ水の侵入を防ぐため | すでに水が漏れてしまった部分をふさぐため |
| 方法 | 屋上や外壁などに、防水材を塗布したり、 シートを貼ったりする | 水がしみ出している部分を注入材などで塞ぐ |
| 施工箇所 | 屋上 外壁 ベランダ・バルコニー 浴室など | 地下室の壁 トンネル コンクリートの継ぎ目 給排水管など |
つまり防水工事は事前対策で、屋上や外壁などに対する水の浸入を防止します。止水工事は事後対応になり、地下室の壁やコンクリート外壁などからの漏水を止めます。どちらも水による建物のトラブルに対応するために必要ですが、混同しないよう注意しましょう。
DIYは可能か?(プロに依頼すべき理由)
基本的に、防水工事のDIYはおすすめできません。なぜなら専門的な知識と正確な施工技術、安全対策などが求められるからです。
たとえば下地処理の精度や防水材の塗布量や乾燥時間などが、施工の品質に影響します。不十分な施工では防水層がうまく形成されず、短期間で水漏れが発生してしまうリスクがあるのです。
また屋上やバルコニーなどの高所作業には、安全対策が必要です。万が一の転落事故や資材の運搬ミスによるケガの危険性があるため、一般の方が行うにはハードルが高い作業になります。
もちろん市販の防水材を使って小規模な補修をすることは可能ですが、あくまで応急処置になります。防水性を長期間保つためには、やはり専門の防水業者に相談し、適切な診断と工事を依頼するのが適切です。
防水工事の種類(工法)と特徴

防水工事にはさまざまな工法があり、それぞれに特徴や向いている施工箇所が異なります。代表的な防水工法は、ウレタン防水とシート防水、FRP防水、アスファルト防水です。それでは、各工法の仕組みや特徴をわかりやすく解説します。
ウレタン防水:複雑な形状にも対応する
ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗って防水層を作る工法です。
- 複雑な形状の屋根やベランダにも対応できる柔軟性がある
- 多くの建物の防水工事で採用されている
液体を塗って硬化させるため、継ぎ目がなく、一体化した防水膜を形成できます。ドレン周りや段差のある場所など、シート工法では対応しづらい形状にも施工がしやすく、密着性も高いのが特徴です。また既存の防水層の上に重ねて塗布する「重ね塗り工法」にも対応できるため、改修工事にも向いています。
ただしウレタン防水のデメリットとして、施工する職人の技術によって仕上がりに差が出ます。豊富な経験と実績のある業者に依頼することが重要です。
ウレタン防水工事をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
シート防水(塩ビ・ゴム):施工が早く品質が安定する
シート防水は、防水性のあるシート(塩ビまたはゴム)を施工面に貼り付ける工法です。
- 工場で製造された高品質な材料を使用する
- 施工後の品質が安定しやすく、施工スピードも早い
あらかじめ製造されたシートを接着剤や機械で固定するだけなので、天候や職人の技術によるムラが少なく、均一な仕上がりが期待できます。また小雨なら中断せずに施工できる場合もあり、特に工期が限られている現場で重宝されます。
一方で、シート防水は細かい場所や複雑な形状には適していません。たとえば角やドレン周りなどでは加工が必要になるため、工夫が求められます。面積の大きい屋上やマンションの共用廊下など、広くてシンプルな形状の場所では非常に有効な選択肢です。
FRP防水:軽量で耐久性が高い
FRP防水は、FRP(Fiber Reinforced Plastics、繊維強化プラスチック)を使用する防水工法です。
- ガラス繊維で補強されたプラスチック素材を使用する
- 軽量でありながら、高い強度と耐久性を備えている
FRPは硬化後に耐荷重性が増すため、ベランダやバルコニーなど、人がよく通行する場所に適しています。さらに施工後の防水層は非常に硬いため、摩耗にも強く、耐用年数が10〜15年と比較的長いです。
一方で、硬化時に臭いが強く出るため、住宅では一時的に窓を閉める必要があります。また広い屋上を施工するとコストが高くなるため、予算を検討してください。狭小部の防水工事には、非常に効果的な工法です。
アスファルト防水:古くから使用されて信頼性が高い
アスファルト防水は、加熱したアスファルトを使って防水層を形成する伝統的な工法です。
- 長く利用されてきた信頼性の高さから、大規模建築や屋上などによく利用される
- 「トーチ工法」「熱工法」「常温粘着工法」などのバリエーションがある
現場に合わせて、工法を使い分けることが重要です。たとえばトーチ工法では、バーナーでアスファルトシートを炙って接着させるため、高い密着性と防水性能が得られます。耐用年数は15〜20年と長く、メンテナンス次第で高いコストパフォーマンスを発揮します。
ただし施工時に高温作業が必要になるため、近隣への配慮や安全の管理が重要です。また施工には職人の熟練した技術が必要であるため、基本的に一般住宅には採用されません。耐久性を重視する大型商業施設や集合住宅などに適した工法です。
防水工事の実際の様子についてはインスタでもご紹介していますので、併せてご覧ください。
防水工事の種類(工法)の選び方

防水工事を成功させるには、「施工箇所」や「建築構造」などの条件に合った工法を選ぶことが重要です。そこで屋上やベランダなどの施工箇所と木造や鉄筋コンクリート造といった建築構造の2つの視点から、適した防水工事の選び方を解説します。
施工箇所(屋上・ベランダ・バルコニー・浴室など)
防水工事の種類を選ぶうえで、施工箇所の特徴に合わせた工法を選ぶことが重要です。施工箇所によって、雨や湿気の量、人の出入り、形状の複雑さなどが異なるためです。
| 施工箇所 | 特徴 | 適した工法 |
| 屋上 | 雨を直に受ける 広くて平坦な面が多い | シート防水(施工が早い) アスファルト防水(耐久性が高い) |
| ベランダバルコニー | 入り組んだ配管やドレンがある 人や物の出入りが激しい | ウレタン防水(複雑な形状に対応できる) FRP防水(硬くて摩耗に強い) |
| 浴室 | 常に湿気が多い | シート防水(床の施工がしやすい) モルタル(タイルの下地になる) FRP防水(摩耗性や耐薬品性が高い) |
上表のように、防水工事では「どこに施工するか」によって選択肢が変わります。費用だけではなく、性能も踏まえて施工箇所に適した工法を選びましょう。
建築構造(木造・S造・RC造など)
建築構造も、防水工事の工法を選ぶ際の大切な判断材料です。建築構造に応じて適切な工法を選ばないと、施工後のトラブルや耐久性の低下を引き起こすリスクがあります。
| 建築構造 | 特徴 | 適した工法 |
| 木造 | 構造体の木材が温湿度や地震によって伸縮・変形する | ウレタン防水(柔軟性が高い) FRP防水(軽量で耐久性が高い) |
| 鉄骨造 (S造) | 接合部や外装材の隙間から水が浸入する | 防水塗装(外装材) シート防水(軽量で施工しやすい) アスファルト防水(耐久性が高い) |
| 鉄筋コンクリート造 (RC造) | コンクリートのひび割れ・継ぎ目から水が浸入する | シート防水(水蒸気を逃がしやすい) アスファルト防水(耐久性が高い) |
建築構造によって、防水層の密着性や膨れのリスクが変わってきます。防水層の膨れに備えるためには、通気工法が有効です。単に「安いから」「施工が早いから」といった理由だけではなく、建物構造の特性を踏まえて工法を選ぶことで防水性を維持しやすくなります。
防水工事の費用相場と耐用年数

防水工事では、工法ごとに費用相場や耐用年数が異なり、維持費にも差があります。長期的な視点で、コストパフォーマンスを見極めることが大切です。ここでは、工法別の工事費用やメンテナンスの頻度、コストパフォーマンスの高い工法をご紹介します。
工法別の工事費用とメンテナンスコスト
防水工事の費用は、工法によって異なります。比較的安価な「ウレタン防水」「シート防水」に対して、「FRP防水」「アスファルト防水」は高めの傾向です。
| 防水工事の工法 | 工事費用の単価 |
| ウレタン防水 | 1㎡あたり4,000~6,000円 |
| シート防水 | 1㎡あたり5,000~7,000円 |
| FRP防水 | 1㎡あたり6,000~8,000円 |
| アスファルト防水 | 1㎡あたり7,000~9,000円 |
※ただし施工箇所や建築構造、気候、利用状況などによって、工事費用は変動します。
防水工事後には、定期的なトップコートの塗布や継ぎ目の補修などのメンテナンス費用がかかります。初期費用だけでなく、維持費も合わせて比較することが重要です。
耐用年数とメンテナンスの頻度
防水工事の種類を選定する際には初期費用だけでなく、耐用年数にも注目すべきです。耐久性が高い工法ほどメンテナンスの頻度を抑えられるため、長期的にはコスト削減につながります。
防水工事の耐用年数とメンテナンスの頻度は、以下の通りです。
| 防水工事の工法 | 耐用年数 | メンテナンスの頻度 |
| ウレタン防水 | 10〜12年程度 | 5年前後 |
| シート防水 | 10〜15年程度 | 10年前後 |
| FRP防水 | 10~15年程度 | 5年前後 |
| アスファルト防水 | 15〜20年程度 | 10年前後 |
※ただし施工箇所の環境や気候、利用状況などによって、耐用年数やメンテナンスの頻度は変動します。
10年で再施工が必要な工法と20年近く保つ工法では、メンテナンスコストに大きな差が出てきます。防水工事の予算を立てる際には、メンテナンスの頻度を減らすことで長期的な負担を軽減できることを覚えておきましょう。
コストパフォーマンスの良い工法
コストパフォーマンスの良い工法を選ぶためには、初期費用とメンテナンスコストのバランスを考慮する必要があります。コストのバランスが良く、多くの現場で採用されている工法は、「ウレタン防水」と「シート防水」です。
ウレタン防水の初期費用は比較的安く、複雑な形状にも対応できるため、戸建て住宅や小規模建築物ではコストパフォーマンスが高くなります。耐用年数が10年以上あり、トップコートを数年おきに塗るだけでメンテナンスが可能です。
シート防水は耐久性が高く、施工が早いため、広い屋上やマンションの共用部などに適しています。材料費はやや高めですが、職人の技術差が出にくく、仕上がりも安定するため、管理がしやすいのもポイントです。
なおFRP防水やアスファルト防水の初期費用は高めで、施工条件や用途を選ぶため、費用対効果を重視する場合には慎重に検討すべきです。施工箇所や建築構造に合った工法を選ぶことで、無駄な出費を抑えられます。
防水工事を依頼する際の注意点

防水工事を安心して依頼する際には、費用以外にも気をつけるべき注意点があります。相見積もりや業者の信頼性、保証内容などに気をつけることで、施工後のトラブルや追加費用のリスクを避けることができます。
相見積り
防水工事を依頼する際は、必ず複数の業者から相見積りを取るようにしましょう。なぜなら同じ工事内容であっても、業者によって金額や工法の提案内容に大きな差が出ることがあるからです。
そこで以下の注意点に気をつけて、各業者の見積もりを比較してください。
- 工事費用が極端に安すぎたり、高すぎたりしないか
- 工法を丁寧に説明してくれるか
- 下地処理や仕上げ処理などの内訳まで具体的に書かれているか
また口頭ではなく、必ず書面で見積書を出してもらいましょう。見積書に工事内容や材料の種類、数量などが明記されていない場合は、工事後に追加費用が発生するトラブルが起こりかねません。相見積りは「価格」はもちろん、工事の透明性を確認する大切なプロセスです。
業者の信頼性
信頼できる業者に依頼することは、防水工事を成功させるために重要です。防水工事の完成度は見た目では分かりにくく、施工不良に気づいたときには既に水漏れなどのトラブルが起きていることがあります。
見積書以外にも、次の注意点に気をつけて業者の信頼性を見極めましょう。
- 業者の公式サイトに施工実績が豊富に掲載されているか、
- 第三者機関の認定を受けているか
- 消費者からの口コミや評判が良いか
- 現地調査時に、工法について丁寧に説明してくれるか
- 自社施工か下請け業者任せか
自社施工であれば品質管理がしやすく、責任の所在も明確です。価格や知名度だけで選ぶのではなく、総合的に信頼できる業者を見極めることが大切です。
保証期間やアフターサービスの有無
防水工事を依頼する際には、必ず保証期間やアフターサービスの有無も確認しましょう。万が一の施工不良に備えるためには、施工保証とアフターサービスが役立ちます。
「材料にのみ保証がある」「施工に対する保証はない」といった工事業者も存在するため、ご注意ください。
- 一般的な防水工事の保証期間は、5〜10年程度である
- 工法や使用する材料によって異なるため、契約前に必ず書面で確認する
- 定期点検の有無やトラブル時の対応方法も調べる
- 口約束ではなく、保証書や契約書に明記されていることを確認する
工事が終わったあとも相談に乗ってくれる業者であれば、長く安心して建物の美観と性能を維持できます。施工後の保証とアフターケアの内容は、業者の信頼性を判断する材料にもなるのです。
まとめ|建物に適した防水工事を選んで長く快適に
防水工事は、建物を雨や湿気から守り、快適性や美観を維持するために欠かせない施工です。工法の種類によって特徴が異なるため、場所や構造に合った選択が重要です。信頼できる業者に、費用や耐用年数を踏まえて適した工法を依頼することで、建物の寿命を延ばし、無駄なメンテナンス費用も抑えられます。
Ti-PROOFでは、専門的な知識と豊富な実績をもとに、お客様の所有する建物に適した防水工事をご提案しています。
確かな品質と安心のアフターサービスで、建物の資産価値を守りますので、まずはお気軽にご相談ください。