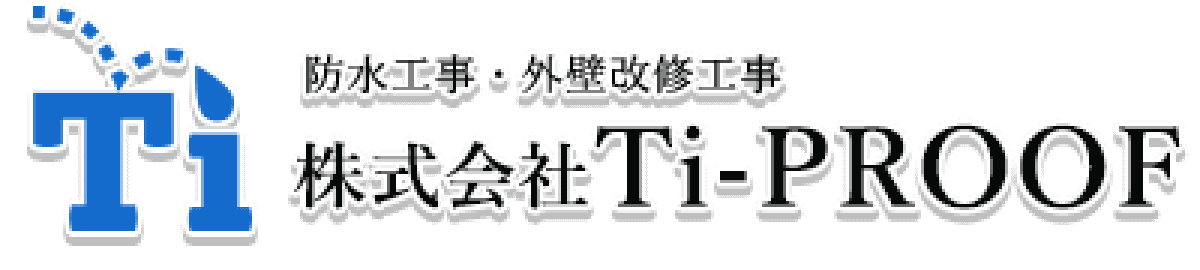シーリング防水工事とは?施工の流れ・費用・耐用年数などを解説


建物の屋根・外壁の防水性を保つうえで欠かせないのが、「シーリング防水工事」です。屋根・外壁の目地やサッシ周りに充填されているシーリング材は、経年劣化によりひび割れや剥がれが生じることがあります。そこで本記事では、シーリング防水工事の役割や流れ、費用、耐用年数など、工事を検討するうえで把握しておきたい情報をわかりやすく解説します。
- シーリング防水工事とは?
- シーリング防水工事の流れ
- シーリング防水工事の費用
- シーリングの劣化症状と耐用年数(交換時期)
- 信頼できる防水工事業者を選ぶポイント
- シーリング防水工事でよくある質問
- シーリング防水工事は信頼できる業者に依頼しよう
シーリング防水工事とは?

シーリング防水工事とは、屋根・外壁の目地やサッシの隙間などにシーリング材を充填して、雨水の浸入や風の吹き込みを防ぎ、建物内部を守るための工事です。防水工事において、重要な役割を果たします。ここでは、シーリングの役割や施工箇所、コーキングとの違い、材料の種類と特徴を分かりやすく解説します。
主な役割
シーリング防水工事の主な役割は、建物の隙間をふさぎ、雨水や湿気の侵入を防ぐことです。特に外壁のつなぎ目や窓まわりは、風雨にさらされやすく、水が入り込むと建物内部の劣化やカビの原因になります。
- 外壁材の隙間(目地)にシーリング材を充填すれば、気密性と防水性を確保できる
- 地震や温度変化による建物の揺れや動きに追従し、ひび割れを防ぐ緩衝材となる
シーリング防水工事は防水性能を高めるだけでなく、建物の寿命を延ばすためにも重要な工程です。
施工箇所
シーリングは、主に建物外部のつなぎ目や接合部に施工されます。
- サイディング外壁の目地
- 窓枠・ドアの周り
- ベランダの笠木まわり
- 外壁と屋根の取り合い部分
たとえば、サイディング外壁ではパネル同士の継ぎ目にシーリングが打たれており、劣化すると雨水が内部に浸入する恐れがあります。また、アルミサッシと外壁のわずかな隙間から雨漏りにつながることがあるため、シーリングでしっかりと保護する作業が必要です。
シーリングは建物外部のつなぎ目や接合部に施工され、雨や風から守る大切な役割を担っています。建物内部の水回り(キッチン・トイレ・浴室など)にも使用される防水工法です。
シーリングとコーキングの違い
シーリングとコーキングは似た言葉ですが、意味合いに違いがあります。建築業界では「シーリング」が現在の一般的な呼び方であり、「コーキング」は以前に使われていた通称です。
もともと「コーキング」は、船の隙間を埋めるために使われていた技術用語で、建築に応用されるようになってからは「シーリング」という言葉が一般化しました。現在では、住宅の防水や気密のために使用される充填材は「シーリング材」と呼ばれ、工事名も「シーリング防水工事」と記載されることが一般的です。
ただし、現場ではいまだに「コーキング」という呼び名が使われることもあり、意味はほぼ同じと考えて差し支えありません。
シーリング材の種類と特徴
シーリング材にはいくつかの種類があり、用途や部位に応じて適切な素材が異なります。代表的な種類は、「変成シリコン系」「ウレタン系」「シリコン系」「アクリル系」などです。
| シーリング材の種類 | 特徴 | 主な用途 |
| アクリル系 | 安価で作業がしやすい | 建物内部の各部屋小規模な補修など |
| シリコン系 | 耐水性・耐熱性・耐久性に優れる | 建物内部の水まわり (キッチン・トイレ・浴室など) |
| 変成シリコン系 | 耐水性・耐候性・接着力に優れる | 建物外部の外壁・屋根サッシまわりや板金など |
| ウレタン系 | 密着性と柔軟性が高い | 建物外部の外壁・屋根下地部材など |
上表のように、シーリング材の種類によって適した施工環境が異なります。適切な材料選びが、防水性を維持するために重要です。
シーリングの重要性については、インスタでもご紹介していますので、併せてご覧ください。
シーリング防水工事の流れ

シーリング材の見た目はシンプルですが、防水工事ではいくつかの重要な工程を丁寧に行う必要があります。下地処理からシーリング材の充填、仕上げまでを正しく行うことで、防水性能を長持ちさせることができるからです。ここでは、一般的なシーリング防水工事の流れを3つのステップに分けて解説します。
既存シーリング材の撤去と下地処理
まず最初の工程は、古くなった既存のシーリング材を撤去し、下地を整える作業です。下地処理が不十分だと、新しく充填したシーリング材が密着せず、早期に剥がれたり、ひび割れたりする原因になります。
- カッターや専用工具で、古いシーリング材をきれいに取り除く
- 施工箇所に残った汚れやホコリも丁寧に清掃する
- 目地の奥までしっかり除去することで、新しいシーリング材が接着しやすくなる
施工後に見えなくなる部分の丁寧な処理こそが、防水工事を成功させるカギとなります。
プライマーの塗布とシーリング材の充填
下地処理が完了したら、次にプライマー(下地の接着剤)を塗布し、シーリング材を注入します。プライマーはシーリング材の密着性を高めるために必要不可欠で、塗らずに充填してしまうとすぐに剥がれてしまうリスクが高くなるのです。
- プライマーを均一に塗る
- 専用ガンでシーリング材を目地の奥までたっぷりと充填する
- 隙間ができないように注意しながら、空気が入らないように作業する
シーリング材の充填はシーリング防水工事において重要な作業であり、施工の品質を左右します。
ヘラによる仕上げと養生
シーリング材の充填が終わったら、ヘラを使って表面を平らに整える仕上げ作業を行います。仕上げ作業の目的は、見た目を美しく整えることだけでなく、シーリング材を建物にしっかり押し付けて密着性を高めることでもあるのです。
- マスキングテープを使って周囲の汚れを防ぐ
- 直線的でキレイな仕上がりを目指す
- 仕上げたら、シーリング材がしっかりと硬化するまで、養生期間を設ける
- 施工環境や天候に応じて、数時間から数日間で硬化する
養生期間中に雨が降ったり、衝撃が加わると施工不良につながるため、天候や工事スケジュールにも十分配慮が必要です。適切に養生することで、耐久性の高い防水性能を実現できます。
シーリング防水工事の費用

シーリング防水工事を検討する際に気になるのが、工事費用ではないでしょうか。工事費用は建物の規模や使用する材料などによって異なります。ここでは「打ち替え」と「打ち増し」の費用相場と費用を抑えるコツについて詳しく解説します。工事の見積もりを取る前の参考情報としてご活用ください。
打ち替えの費用相場
シーリングの「打ち替え工事」の費用相場は、1mあたり900円〜1,200円程度です。30坪程度の戸建て住宅(外壁の目地が200m程度)なら、18万〜30万円程度がかかります。
- 既存の劣化したシーリング材を全て撤去し、新たにシーリング材を充填する
- 高い防水性と耐久性を期待できる
- 打ち増しよりも手間がかかるため、工期と費用がやや高くなる
外壁全体の劣化が進んでいるケースや耐久性を重視したい場合に、打ち替え工事が適しています。
打ち増しの費用相場
打ち増し工事の費用は、1mあたり500円〜900円程度です。30坪程度の戸建て住宅(外壁の目地が200m程度)なら、10万〜16万円程度がかかります。
- 既存シーリング材の上から新しいシーリング材を追加で充填する
- 打ち替えと比べて工程が少ないため、費用を抑えやすく、工期も短縮できる
- 劣化が進んだ目地に打ち増しを行っても、十分な防水効果を得られない場合がある
シーリングの打ち増しは、軽度のひび割れを短期的に補修する目的で行われます。費用を抑えながらも、必要最低限の防水性を確保したい場合に向いている工法です。
工事費用を抑えるコツ
シーリング防水工事の費用をできるだけ抑えるには、以下のポイントを意識することが大切です。
- 外壁塗装と一緒に依頼する
- 複数の業者から見積もり(相見積もり)を取る
- 打ち替えと打ち増しの箇所を明示してもらう
足場代は、外壁工事で大きなコストを占めます。防水工事と塗装工事を同時に行えば、足場設置費用を1回分にまとめられるため、大幅なコスト削減につながります。
また、同じ工事内容でも業者によって価格設定が異なるため、比較することで適正価格が見えてきます。特に、地域密着型の業者は大手と比べて中間マージンが少なく、費用を抑えやすい傾向があります。
さらに、見積もりを受け取ったら、「どの部分が打ち替えで、どの部分が打ち増しか」を明確に提示してもらうことで、不要な費用を削減できます。納得できる価格で工事を行うためには、信頼できる業者に依頼しましょう。
シーリングの劣化症状と耐用年数(交換時期)

シーリング材は時間の経過とともに劣化し、防水性が低下します。見た目には小さなひび割れでも、放置すると建物内部の雨漏りや腐食につながることがあります。ここでは、劣化のサインや放置するリスク、交換時期の目安についてわかりやすく解説します。
ひび割れ・肉やせ・剥離などのサイン
シーリング材の劣化を示すサインには、「ひび割れ」「肉やせ」「剥離」などがあります。劣化の症状が出ている場合は、防水性が著しく低下している可能性が高いため、早めの対応が必要です。
- ひび割れ:紫外線や風雨によって表面が硬化し、弾力を失うことで発生する
- 肉やせ:施工時に比べて厚みが減っている状態で、典型的な経年劣化の現象である
- 剥離:シーリング材が目地の両端から剥がれ落ちて、水の浸入経路になる
劣化のサインを放置してしまうと、建物内部の防水層や構造部分のダメージが大きくなるリスクがあるため、発見したら速やかに補修を検討しましょう。
劣化を放置する悪影響
シーリング材の劣化を放置すると、さまざまな問題を引き起こします。
- 雨水の浸入による下地材の腐食やカビの発生
- 構造体のダメージによる断熱性の低下
たとえば、シーリングの剥がれた目地から雨水が侵入して、木材が腐食してしまうと、白アリ被害のリスクが高くなります。また、断熱材が濡れてしまうと、住宅全体の断熱性能が落ち、冷暖房効率が悪化します。
以上のことから、劣化したシーリングを放置にしておくと補修費用だけでなく、建物全体のメンテナンスコストがかさむ原因にもなります。早めに劣化を発見して、早めに対処することが肝心です。
耐用年数(交換時期)の目安
一般的に、シーリング材の耐用年数は5~10年程度です。ただし、実際の寿命は使用するシーリング材料の種類や施工環境などによって異なります。
- アクリル系:5~7年程度
- 変成シリコン系:10〜15年程度
- シリコン系:5~10年程度
- ウレタン系:5〜10年程度
直射日光が当たる場所や風雨にさらされやすい部位では、劣化が早まる傾向にあります。施工から5年程度の周期で、プロによる点検を依頼することがおすすめです。耐用年数を過ぎてしまうと、見た目に問題がなくても建物内部で劣化が進んでいる場合もあります。
信頼できる防水工事業者を選ぶポイント

シーリング防水工事を成功させるためには、適切な業者選びが不可欠です。施工技術だけでなく、見積もりの明確さやアフターサービスも重要な判断材料です。ここでは、信頼できる業者を見極めるために確認しておきたい3つのポイントを解説します。
相見積もりを取る
シーリング防水工事を依頼する際は、必ず複数の業者から見積もり(相見積もり)を取りましょう。なぜなら、同じ工事内容でも業者によって価格や提案内容が異なるからです。
たとえば、ある業者では30万円の見積もりでも、別の業者は20万円台で同じ工事内容を提示することがあります。また、材料のグレードや工程の詳細が含まれていない見積書もあるため、価格の根拠を確認することが重要です。
相見積もりを通じて、費用だけでなく説明の丁寧さや信頼感も判断できます。複数の業者を比較して、納得のいく業者を選ぶことが大切です。
施工実績を調査する
業者選びでは、過去の施工実績を確認することが信頼性の判断材料になります。シーリング防水工事の実績が豊富な業者には、さまざまなトラブルに対応してきた経験があるため、高い技術力や対応力を期待できるからです
- 公式サイトで施工前後の写真や具体的な工事内容を発信している業者を探す
- 同じ建物の種類(戸建て住宅やマンションなど)の施工実績を確認する
防水工事業者の施工実績を調査することで、工事の質や仕上がりのイメージを事前に把握できます。
施工保証とアフターサービスを比較する
シーリング防水工事後の経年劣化やトラブルに備えて、施工保証とアフターサービスの内容も比較してください。特に、施工後に不具合があった場合に「どこまで無償で対応してもらえるか」が重要です。
たとえば、5〜10年の保証期間を設けている業者であれば、一定期間内の雨漏りや剥離などに迅速に対応してもらえるため、安心して依頼できます。また、保証書の発行や定期点検の有無も確認しておくと安心です。
施工保証とアフターサービスが充実している業者を選ぶことで、工事後も長期的に安心して住み続けることができます。
シーリング防水工事でよくある質問
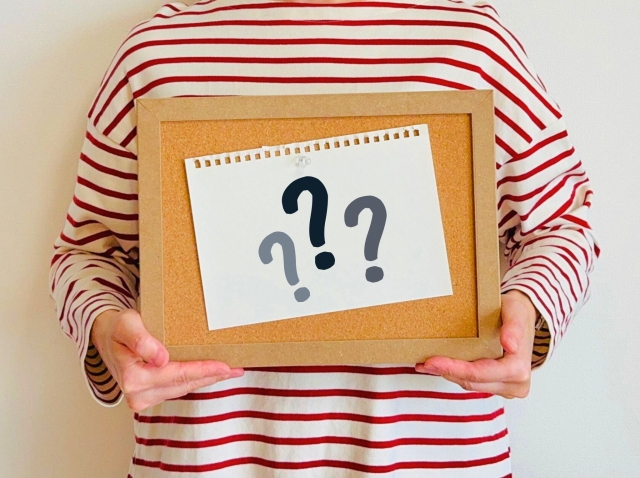
シーリング防水工事を検討していると、天候やDIY、定期点検、他の防水工法との違いなど、さまざまな疑問が浮かぶものです。ここでは、よくある質問に対して分かりやすく丁寧に解説します。初めて工事を依頼する際も安心して判断できるように、ぜひ参考にしてください。
雨の日でも工事はできますか?
いいえ、基本的にシーリング防水工事は雨の日に実施できません。シーリング材は湿気や水分に弱く、雨天時に施工すると密着不良や硬化不良を引き起こす恐れがあるからです。
- 雨で表面が濡れていた場合、シーリング材がしっかりと付着しない
- 施工が不十分だと、施工後に剥離やひび割れが起こりやすくなる
工事は必ず乾燥した状態で行う必要があり、天気予報を見ながら工程を調整するのが一般的です。梅雨や台風の時期を避けて施工時期を選ぶと、スムーズに工事が進みやすくなります。
DIYで対応できますか?
はい、小規模な補修であれば、DIYで対応できる場合もあります。ただし、基本的には専門業者に依頼するのが安全で、特に外壁の高所作業や複数箇所の補修を伴う場合は知識と経験が求められます。
- サッシ周りの簡単な隙間埋めであれば、市販のシーリング材で対応できる
- 目地の打ち替えには、古いシーリングの除去やプライマーの塗布などが必要になる
- 正確な作業をしなければ、施工したシーリング材がすぐに劣化してしまう
DIYは劣化の応急処置にとどめ、長持ちさせたい場合や広範囲に劣化が広がっている場合は、専門業者へ依頼するほうが安心です。
定期点検の頻度はどれくらいですか?
5年くらいの周期で、施工したシーリング材を定期的に点検してください。シーリング材には5~10年程度の耐用年数を期待できますが、施工環境(紫外線や風雨、温度差)によって劣化のスピードが変わるからです。
- 築10年を過ぎた住宅では、シーリングのひび割れや肉やせが始まる
- 専門業者による無料点検サービスを活用すれば、劣化の状態を把握できる
したがって、築10年を超える建物では定期点検の重要性が増します。劣化を放置せずに定期的に点検することで、大きなトラブルを未然に防ぐことが可能です。
他の防水工法との違いはありますか?
建物の隙間を埋める「線的な防水」であるシーリング防水工事に対して、ウレタン防水・シート防水・FRP防水・アスファルト防水工法などは「面的な防水」です。
- シーリング材は、目地や接合部といったピンポイントの防水に特化している
- 他の防水工法は、施工箇所の全体に塗膜を形成する
- 一般的に、他の防水工法と組み合わせてシーリング材が使われる
つまり、シーリング材は、防水工事において補完的な役割を果たします。シーリング防水工事は、建物の細かな箇所の防水性を高めるために欠かせません。
シーリング防水工事は信頼できる業者に依頼しよう
シーリング防水工事は、建物の防水性を維持するために欠かせません。劣化を放置すると雨漏りや構造体の腐食など、深刻な被害につながる恐れがあります。定期的な点検と信頼できる専門業者への工事の依頼が、建物の耐久性や快適性を保つために重要です。気になる症状があれば、まずは無料点検見積もりから始めてみましょう。
Ti-PROOFでは、専門的な知識と豊富な実績をもとに、お客様のベランダに適した防水工事をご提案しています。
確かな品質と安心のアフターサービスで建物の資産価値を守りますので、まずはお気軽にご相談ください。