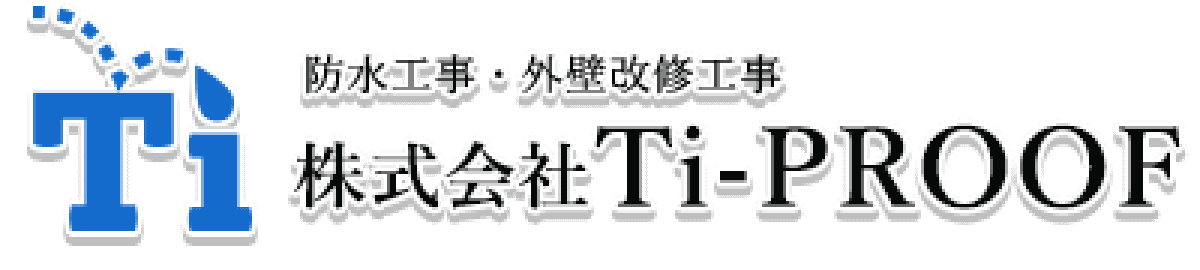屋上防水工事の種類とは?費用相場、施工手順まで徹底解説


屋上防水工事は、建物を雨水や湿気から守り、耐久性を維持するために欠かせない工事です。防水層が劣化すると、雨漏りや構造部材の腐食などの被害を招く恐れがあります。そこで本記事では、屋上防水工事の必要性から種類、費用、手順までについて分かりやすく解説します。信頼できる工事業者の選び方も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
屋上防水工事とは?必要性と放置リスク

屋上防水工事は、建物を雨や雪から守るために欠かせない工事です。防水層が劣化すると雨漏りや構造部分の損傷につながります。ここでは、防水工事の目的や役割、劣化のサイン、放置した場合のリスクについて詳しく解説します。
目的と役割
屋上防水工事の目的は、建物の内部に雨水が侵入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばすことです。屋上は外壁や窓よりも直接的に雨や紫外線にさらされる時間が長く、特に防水性能が求められます。
- 防水層が正常に機能していれば、コンクリートや鉄骨などの構造材へ水分が浸入するのを防ぎ、腐食や劣化を抑えられる
- マンションや商業ビルでは、屋上の防水層が劣化すると短期間で雨漏りが発生する
- 雨漏りは、室内の天井や壁紙のシミだけでなく、電気設備の被害も引き起こす
防水工事は単なる雨漏り対策ではなく、建物全体の安全性や快適性を守るための重要な役割も担っています。定期的な点検と適切な施工により、防水層の寿命を延ばし、長期的な修繕コストも抑えられるのです。
防水層の劣化症状(工事のタイミング)
防水層の劣化は、見た目や感触である程度判断できます。
- 劣化症状には表面のひび割れや膨れ、色あせ、剥がれ、コケ・カビの発生がある
- 紫外線や温度変化、雨水の影響などによって、防水層の劣化が徐々に進行していく
たとえば、ウレタン防水では表面に細かいひびが入りやすく、シート防水では継ぎ目の浮きや剥がれが目立つことがあります。防水層の耐用年数は工法や施工環境によりますが、一般的には10〜15年程度が目安です。施工から10~15年を過ぎる頃に防水層の劣化が進み、軽微な補修では対応できなくなっていきます。
したがって、防水層の劣化症状が出始める初期段階が、理想的な防水工事のタイミングです。早めの施工によって被害の拡大を防ぐことで、工事費用を抑えられます。防水層の劣化症状については、動画でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
劣化を放置するリスク
防水層の劣化を放置すると、雨漏りや構造部材の腐食といった深刻な被害が発生するリスクが高くなります。特に鉄骨造の建物では、内部に水が入り込むことで錆びが進行し、強度の低下を招く危険性があるのです
また、木造の建物で雨漏りが発生すると、腐朽やシロアリ被害のリスクが高まります。 雨漏りが室内にまで達すると、天井や壁のクロスが剥がれるだけでなく、カビが発生しやすくなります。カビは見た目の問題だけでなく、アレルギーや呼吸器系の健康被害を引き起こすリスクもあります。さらに、漏水による電気系統のショートや漏電事故の危険性もあるのです。
以上のように、防水層の劣化を放置してしまうと修繕費用の増額だけでなく、居住者や利用者の安全にも悪影響をもたらします。早期の点検と適切な防水工事によって、建物と人間の暮らしを守ることが重要です。
屋上防水工事の種類と特徴

屋上防水工事の種類によって、特徴が異なります。工法によって適した施工環境や耐久性、コストパフォーマンス、メンテナンス性などが変わるため、違いを理解しておくことが重要です。
ウレタン防水(密着工法・通気緩衝工法)
ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗布して硬化させ、防水層を作る工法です。密着工法と通気緩衝工法があります。
| ウレタン防水の工法 | 仕組み | 特徴 |
| 密着工法 | 下地に直接ウレタン樹脂を塗布する | 施工が簡単で費用を抑えやすい 小規模な屋上や補修に向いている |
| 通気緩衝工法 | 下地との間に通気層を設ける | 内部の湿気を逃がし、膨れや剥がれを防ぐ |
ウレタン防水は、形状が複雑な屋上でも対応可能で、つなぎ目のない防水層ができるのがメリットです。ただし、紫外線や摩耗に弱いため、トップコートの定期的な塗り替えが必要になります。適切なメンテナンスを行えば、10~12年程度の耐用年数が期待できます。
シート防水(塩ビシート・ゴムシート)
シート防水は、防水性の高いシートを屋上に敷き詰めて施工する方法です。
主に、塩ビシートやゴムシートが使用されます。
- 塩ビシート:耐候性や耐久性に優れ、熱で接着するため継ぎ目からの漏水リスクが低い
- ゴムシート:柔軟性が高く、下地の動きに追従しやすい
シート防水の施工期間は比較的短く、工場や大型施設など広い面積の屋上にも向いています。ただし、突起物の多い屋上や複雑な形状などには対応できません。定期的な点検を行えば、10~15年程度の耐用年数が期待できます。
FRP防水
FRP防水は、繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)を使用し、硬化後は非常に強固な防水層が形成されます。
- 軽量かつ耐衝撃性に優れ、歩行頻度の高い屋上やバルコニーに向いている
- 硬化が早く、短工期で仕上げられる
ただし、広い屋上よりも小規模の面積への施工が一般的で、紫外線による劣化を防ぐためトップコートの定期塗装が必要です。適切なメンテナンスで、10〜15年程度の耐用年数が期待できます。
アスファルト防水
アスファルト防水は歴史の長い工法で、耐久性と防水性が高く、公共施設や大型建築物などに採用されています。
- 加熱したアスファルトを複数層に重ねる
- 分厚い防水層を形成し、長期間建物を保護する
- 重量があるため構造の強度が必要になる
- 施工には熟練した技術が求められる
費用や工期は他工法に比べやや高めですが、15~20年程度の耐用年数も期待できる信頼性の高い工法です。
屋上防水工事の費用と見積もり

屋上防水工事の費用は、採用する工法や防水層の劣化状態などによって大きく変わります。1㎡あたりの単価は数千円単位で異なり、面積が広いほど総額が高くなります。ここでは、工法別の費用相場や費用を左右する要因、相見積もりのチェックポイントを解説します。
工法別の費用相場(1㎡あたり)
屋上防水工事費用の相場は、工法によって明確な差があります。
- ウレタン防水 :1㎡当たり3,000〜7,000円程度
- シート防水 :1㎡当たり4,000〜8,000円程度
- FRP防水 :1㎡当たり6,000〜9,000円程度
- アスファルト防水:1㎡当たり7,000〜10,000円/㎡程度
ただし、工法を選定する際は費用だけでなく、耐用年数やメンテナンス性を総合的に考えることが大切です。
費用を左右する要因(施工の面積・環境・劣化状態)
防水工事の総額は、単価だけでなく施工条件によっても変動します。
- 施工面積:広いほど材料費や人件費が増えるが、単価はやや下がる
- 施工環境:資材搬入経路や周辺環境に応じて、費用が加算される
- 劣化状態:防水層や下地の劣化が進んでいる場合は撤去・補修費用が必要になる
たとえ同じ面積でも、「軽度の劣化でアクセスしやすい現場」と「重度の劣化で高層階の現場」では、工事費用の総額に数十万円の差が出ることもあります。
相見積りのチェックポイント
屋上防水工事では、複数の業者から見積りを取ること(相見積もり)が重要です。
- 単価だけでなく、工法の種類や使用する材料、施工範囲、保証内容まで確認する
- 見積書に「一式」とだけ記載されている場合は、具体的な内訳を必ず依頼する
- 施工保証の年数と範囲(「防水層のみ」または「下地まで含む」)も比較する
- アフターメンテナンスの有無や点検の頻度が明記されているかもチェックする
価格が安くても保証期間が短かったり、材料のグレードが低かったりすると、長期的には割高になる場合があります。費用と品質、保証条件を総合的に判断して、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
屋上防水工事の手順と工期

屋上防水工事は、事前調査から引き渡しまでに複数の工程を経て進められます。適切な順序と作業の精度が、防水性に影響を与えます。ここでは、防水工事の手順と工期、季節による影響について解説します。
事前調査と劣化診断
屋上防水工事は、まず事前調査と劣化診断から始まります。建物に適した工法や施工の範囲を決めるために欠かせない工程です。
- 専門業者が、屋上で防水層のひび割れや剥がれ、膨れ、汚れ、コケの発生などをチェックする
- ドレン(排水口)の詰まりや下地の状態も確認する
- 表面だけでなく下地まで劣化している場合は、下地の補強や全面改修が必要になる
施工前に現状を正確に把握することで、無駄な工事や不十分な施工を避けて、工事費用を減らしやすくなります。
下地処理と防水層施工
診断結果に基づいて、下地処理を行います。具体的には、古い防水層の撤去やひび割れの補修、清掃などの作業です。下地処理が不十分だと防水層の密着性が低下し、早期に剥がれや漏水が起こるリスクが高くなってしまいます。
下地処理に続いて、防水層を施工します。
- ウレタン防水 :液体状の樹脂を複数回塗り重ねる
- シート防水 :シートを敷き詰めて接着する
- FRP防水 :ガラス繊維で補強した樹脂を塗布して硬化させる
- アスファルト防水:アスファルトを加熱して複数層に積み重ねる
いずれの工法でも、均一な厚みと丁寧な作業が耐用年数を維持するために重要です。
仕上げと点検・引き渡し
防水層の施工が完了すると、トップコートなどの保護層を塗布して仕上げます。保護層には紫外線や摩耗から防水層を守る役割があり、工法によっては数年ごとの塗り替えが必要です。
仕上げ後は施工箇所の点検を行い、接着の不良や未塗布の箇所を確認します。
- 水を流す散水試験を行う場合は、漏水がないことを確認してから施主に引き渡す
- 引き渡し時には、施工の保証書や記録などが手渡される
施工の保証書や記録があると、万が一不具合が発生した際の対応がスムーズになります。
一般的な工期と季節による影響
屋上防水工事の工期は、規模や工法によって異なります。
- 一般的な住宅の屋上(100㎡前後):1週間前後で済む
- 広い面積や激しい劣化の屋上 :1週間以上かかることもある
また、季節や天候も、工期に影響します。
- 雨天や強風時は施工ができない
- 梅雨や台風シーズンは工期が延びやすくなる
- 寒冷地では冬季に施工が難しい
- 春や秋の穏やかな気候が防水工事に適している
スムーズな施工のためには、季節と天候を考慮してスケジュールを調整しましょう。
屋上防水工事の業者選びと長持ちさせるコツ

屋上防水工事の仕上がりと耐用年数は、施工する業者の技術力や対応によって大きく変わります。施工後の定期点検やメンテナンスを適切に行うことで、防水性能を長期間維持できます。施工保証やアフターメンテナンスも重要です。
信頼できる防水工事業者の選び方
屋上防水工事は専門性が高く、技術や経験の差が仕上がりを左右します。そのため、実績が豊富で施工事例を公開している業者を選ぶことが大切です。
- 過去の施工事例や施工方法を紹介している業者は、信頼性が高い
- 見積書の内訳や使用する材料、保証内容を明記しているかも重要な判断基準になる
- 訪問時の対応や説明の分かりやすさも、業者の誠実さを判断するポイントになる
同じ金額でも、業者によって工事の内容や保証の範囲が異なることは珍しくありません。複数の業者から見積もりを取って、価格だけでなく品質や保証条件も含めて総合的に比較しましょう。
定期点検とメンテナンス
屋上防水工事は一度施工して終わりではなく、施工後の定期点検とメンテナンスが防水性能の維持に不可欠です。
- 施工から3〜5年ごとに定期点検を行えば、防水層のひび割れや剥がれ、排水口の詰まりなどを早期に発見・補修できる
- トップコートが摩耗して紫外線による劣化が始まる前に再塗装すれば、防水層本体の寿命を延ばせる
- メンテナンスを怠って、小さなひび割れから大きな雨漏りが発生すると、大規模な修繕が必要になる
定期点検やメンテナンスでは、施工業者や第三者の専門業者に依頼するのが安心です。費用はかかりますが、長期的には修繕コストの削減につながります。
施工保証とアフターメンテナンスの重要性
施工保証は、防水工事後の一定期間、施工箇所の不具合を無償で修理する制度です。
- 施工保証があることで、不具合が発生しても安心して対応を受けられる
- 保証期間は工法や材料によって異なりますが、一般的には5〜10年程度である
アフターメンテナンスが充実している業者に依頼すれば、定期点検や簡易補修を継続的に行ってくれるため、防水性能を長持ちさせられます。
- 保証期間中に軽微な劣化を補修することで、大規模修繕を回避できる
- 契約前に保証の期間や内容、アフターメンテナンスの有無を必ず確認する
施工保証とアフターメンテナンスで施工後も責任を持って対応してくれる業者を選べば、長期的な安心感を得られます。
屋上防水工事を信頼できる業者に依頼しよう
屋上防水工事は、建物の寿命や快適性を守るために欠かせません。適切な工法と確かな技術を持つ業者の選択が、長期的な防水性能の維持につながります。施工後も定期点検やメンテナンスを行い、早期対応を心がけることで、余計な修繕費用を防ぎながら安心できる環境を保ちましょう。
Ti-PROOFでは、専門的な知識と豊富な実績をもとに、お客様の所有する建物に適した防水工事をご提案しています。
確かな品質と安心のアフターサービスで、建物の資産価値を守りますので、まずはお気軽にご相談ください。